ヒューライツ大阪は
国際人権情報の
交流ハブをめざします
- TOP
- 国際人権基準の動向
- 国際人権ひろば
- 国際人権ひろば No.172(2023年11月発行号)
- 「男性の性暴力被害」その声を聴くために
国際人権ひろば No.172(2023年11月発行号)
人権の潮流
「男性の性暴力被害」その声を聴くために
男性の性暴力被害について、「どれくらいの被害があるのか?」「どのような被害があるのか?」「男性被害者の特徴は?」と取材で尋ねられるようになったのは、ほとんど関心を向けられず研究の蓄積もなかったこれまでを振り返ると、日本社会の変化の兆候かもしれない。だが、さまざまな人生、背景をもつ一人ひとりの被害者の体験を抽象化、平均化した被害率、被害形態、性別カテゴリーに基づいた被害特徴を伝えることで、本当に男性の性暴力被害に対する疑問に答えることになるのか悩ましくも感じる。
2023年にBBCがジャニー喜多川氏による長期間続いた性暴力を報じてから、日本の報道も格段に増えて、関心が向けられている。ジャニーズ事務所内の権力関係の中で長期間の加害が続いていたこと、またほとんど報道されなかったことの弊害は大きく指摘されている。記者会見を見ると、ほとんど性暴力について知識がないと思われる記者たちが、一会社の単なる不祥事を追求するような姿勢が見える。一人の特殊な加害者がいたという話ではなく、そのような個人が守られ、その会社が存続できる日本社会なのだと思う。
日本社会は性暴力被害者支援には十分な予算を割いてこなかったし、むしろ削減するように訴えた国会議員もいた。また、子どもの安全や教育の問題、女性やマイノリティへの差別といった、さまざまな背景を抱える個人の権利、人権を守ってこなかった。金や権力を持った男(特権的な男性)の加害が隠蔽される一方で、被害に遭った者を黙らせてきたのが日本の男性優位な社会の一面である。そして男性の性暴力被害もまた男性優位な社会がもたらした社会問題である。
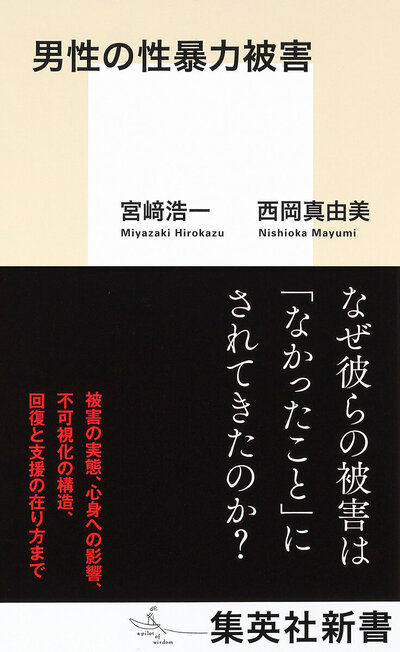
宮崎 浩一、西岡 真由美 著
『男性の性暴力被害』(集英社新書、2023年10月17日)
不可視性
男性の性暴力被害が抱える問題の一つはその不可視性である。不可視性とはつまり見えない問題、あるいは、見えづらい問題となっていることだ。その見えなさを象徴的に表しているのが、犯罪統計である。日本の性犯罪に関する刑法では、男性が挿入を伴う性暴力被害(いわゆるレイプ被害)の被害者にはならないことになっていた。2017年に刑法が改正されるまでの「強姦罪」では、「女子を姦淫した者」が罪に問われていたので、法律上、男性は被害者にはなり得なかったし、その加害者は男性でしかなかった。そのため、全国の警察が報告した刑法犯の検挙状況を表す「犯罪統計」に男性のレイプ被害は計上されていなかった。つまり、存在しないことになっていたのである。
性暴力の定義を国連は「身体の統合性と性的自己決定を侵害するもの」としている。これに照らせば、その被害者となる者の属性は関係しない。だが、男性は加害者、女性は被害者という関係の中で見られてきた。また、セクシュアリティの点から見ると、男性が挿入する側で女性が挿入される側というところもある。そして、ここには、男女間、つまり異性間の性行為が前提とされていることもわかる。さらに言えば、この社会に男と女という性しかないという男女二元論によって組み立てられている。
性暴力という言葉は、同意のない性的な言動を指している。そして、この言葉は80年代から女性たちが作り、広げていった言葉である。今日の性暴力にまつわるさまざまな言葉が使われるのは、女性運動やフェミニズムに負うところがほとんどである。「男性の」とつけないと特定の被害者属性が見えてこないのは、男性被害者にジェンダー、つまり、男女の権力関係が影響しているからである。そのため、男性被害者の「不可視性」は、性差別のある社会の問題として考えられる。
男性が被害に遭うと、これらの社会的な常識や社会規範に違反していることになってしまう。そのため、男性が性暴力の被害に遭うことが想像されなかったりする。加害者が男性であれば、それは同性愛の問題として追いやられ、加害者が女性であると、望ましいこととして男女間の性行為として被害に遭った男性が能動的に関わっていたと見ようとする。このような矛盾した状況に男性被害者は置かれるのである。社会規範の違反によって被害者が不可視になっている状況は、男性被害者がいないとすることで社会規範を温存することに役立つ。例えば、私がある学会で男性の被害について発表した際に、少し離れたところからニヤニヤしながら見ていた人がいた。被害率や被害形態、被害後の特徴を伝えたところ、どうもピンとこないようだった。このピンとこない状態は個人の偏見だけでは済まされないものがあると思う。それは被害事実や実態を提示しても、「男性は性暴力被害に遭わない」という誤った信念が半ば正当性を持ってしまう社会だからなのではないだろうか。
このような状況を生んでいるのは極めて社会的な問題だが、被害は個人的な出来事でもある。個別性のある被害体験を整理していく際に、社会や加害者に問題や責任を返すよりも、自分が間違っていたのではないか、あるいは、自分の性自認、性指向が違うのではないかと、被害者側が思い悩むことは稀なことではない。それは、男性被害者を存在させないように仕向けてきた社会の効果である。その結果として被害を訴えられなかったり、相談しづらかったりする。
社会を構成している我々が見てこなかったことが不可視を作っているのだから、単に被害者の実態を抽象的に知るだけでは理解することが難しいのである。
聴くために
現在、日本の性犯罪刑法はジェンダー中立的になってきている。2017年に加害者・被害者の性別規定が「強制性交等罪」でなくなったし、2023年の改正では「不同意性交等罪」で、挿入するものがペニスに限定されることが無くなり、身体の一部や物を挿入することも含まれるようになった。理念的には中立的だが、実際の運用や社会の認識との間には大きく隔たりがあると思われる。今年7月に行われた性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議では「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」として政府は今後の方針を示した。その中では、研修を充実させることが盛り込まれたりすることなどが示されている。しかし、これまでに十分な人材育成を怠り、予算も割いてこなかった日本で、誰が研修をするのか、誰が支援をするのかは難しい課題となるだろうと思う。先述したように男性の性暴力被害を見ていくと、被害者個人の抱える問題と社会の問題・歴史的な問題が複雑に絡まっている。そのような状況で、我々に何ができるだろうか。
理念的に中立性のある刑法や、性暴力の定義自体は言葉として理解できるものの、実際に「?の」と付記されて初めて認識できる被害がある。おそらくそういった被害を見聞きしたときには、ピンとこないことや、疑問や違和感があると思う。それらの感覚を丁寧に扱うことから始まるのではないだろうか。自分がわからないこと、受け止められないことについて、常識的な性別観などの社会通念を当てはめて理解しようとすることは簡単なことだが、それによって性差別を温存する社会の構造を維持するように加担する可能性もある。そのため、「聴く」ということ、当事者が何を訴えているのかを理解しようと努めることが必要であると思う。その出来事は、#MeTooのような運動であるかもしれないし、報道される事件かもしれない、あるいは、日常の中にある性を侵害するような出来事にあるかもしれない。当事者の声を聴くということは、被害事実を客観的に認定するような姿勢ではなく、個人の体験がまさに事実であること、それをそのまま受け止めようとすることだと思う。その際に生じる違和感はおそらく当事者の言葉が理由ではなく、自分自身が持つ社会規範や常識との不一致だ。そこに気づくことが、不可視にさせる社会的な力に抗うことに繋がると思う。
