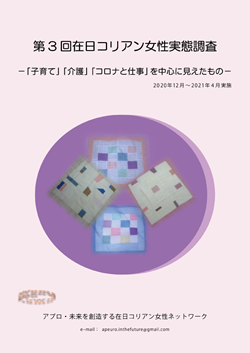ヒューライツ大阪は
国際人権情報の
交流ハブをめざします
3/18 共催学習会「『在日コリアン女性実態調査』から見えたもの:当事者による当事者への調査の意義と課題」を開催しました。
複数のアイデンティティが重なり合うことによる差別や不平等を受ける人びとの人権に目を向けようとする流れが、人権の分野で広がってきました。その状況を変えるべく当事者が声をあげてきましたが、公的機関をはじめとする日本の社会の取り組みはなかなか前進しません。
そのような中で、在日コリアン女性の当事者団体である「アプロ・未来を創造する在日コリアン女性ネットワーク」(略称:アプロ女性ネット)が、自分たちの手で、「子育て」「介護」「コロナと仕事」にフォーカスした3回目の実態調査を行い報告書にまとめました。その機会をとらえて、ヒューライツ大阪とアプロ女性ネットの共催学習会を3月18日にオンラインで開催しました。アプロ女性ネット代表で関西大学非常勤講師の李月順(り うぉるすん)さんが調査の概要とそこから見えてきたものを報告し、社会意識調査の専門家である東京大学准教授の永吉希久子さんが今回の調査の意義と課題についてコメントしました。参加者は51人でした。
報告とコメントについての要旨は次のとおりです。
李月順さんの報告
「拡がり、つながり、ともに立ち向かう」を合言葉に」
<調査の背景と今回の調査の概要>
「アプロ女性ネットは、2004年の「在日朝鮮人女性実態調査プロジェクト」から出発し、2016年に「第2回在日コリアン女性実態調査―生きにくさについてのアンケート」を実施した。今回は2020年実施の「第3回在日コリアン女性実態調査―「子育て」「介護」「コロナと仕事」を中心に見えたものー」の結果から見えたものをいくつかに絞って紹介する。
まず、実態調査に取り組んだ理由は2つ。1つは、日本社会で不可視化されてきた私たち(在日コリアンであり、かつ女性である)の問題を可視化する。2つ目は、国連女性差別撤廃委員会からのマイノリティ女性の実態把握をするようにという勧告を日本政府が無視しつづけているからである。
調査は、満20歳以上で、「国籍にかかわらず朝鮮半島にルーツがある日本に住む女性」を対象とした。調査方法としては(1)配布アンケートは旧植民地出身者を想定、(2)オンライン調査(韓国語)は韓国からのニューカマーを想定、(3)インタビュー調査の3つのパートで構成した。調査の詳細は、報告書を参照してほしい。ここでは配布アンケートを中心に報告する。(報告書の入手方法等は文末)
配布アンケートは、知人やネットワークを活用し、1,157部配布し553部を回収した。オンライン調査は133人の回答を得た。インタビューはのべ19人の協力を得て、アンケート調査を補完することにした。当初、目標数をもう少し多く設定していたが、コロナ・パンデミックのために活動が制限され、このような結果となった。配布アンケートの属性は、50代が最も多く、60代、40代と続く。国籍は、韓国籍が約74%、朝鮮籍が約16%、日本籍が1割、その他が1人。外国籍の在留資格は、特別永住が9割を超え、一般永住が約6%であった。
<7割以上の女性が自分の子どもへのヘイトスピーチが心配>
そのうち子ども(18歳以下)がいる158名に尋ねた「養育での心配や困っていること」の結果を紹介する。「学校・幼稚園・保育所で民族名・本名で通っている」のは6割を超える高い割合だが、「民族学校に通わせている」が47%いたことが関係している。一方「子どもの将来において就職や結婚で差別されるか」には全体で6割を超える人が「大いにある」「少しある」心配と回答している。「コロナ禍で教育費の負担が増えたか」には、全体で「あてはまる」「ややあてはまる」が8.4%だが、朝鮮学校に限ると24.3%。この背景には「高校無償化」排除や自治体の補助金停止や削減の中でコロナ禍により一層負担が増していると思われる。さらに「子どもがヘイトスピーチを受けるか」については7割を超える人が、心配が「大いにある」「少しある」と回答している。
<高齢者介護の現状、コロナと生活への影響>
次に高齢者の介護についてであるが、在日コリアンの高齢化率(韓国・朝鮮籍者総人口に占める65歳以上の人口)は3割弱で、日本全体とほぼ同じである。介護経験者は回答者全体の3割強であったが、自分の父母の介護が5割近くで一番多く、次に義父母で約35%であった。介護保険サービス利用料は本人が払う場合が一番多かったが、生活保護の介護扶助、夫やパートナー次に私(回答者)が続く。この背景には、かつての国民年金からの制度的排除と救済措置がないため無年金者がいることもあるだろう。また、介護保険の保険証は約6割が日本名を使っている。
その次に仕事や生活に新型コロナが与えた影響であるが、雇用形態は正社員が4割、アルバイト・パートタイマーが3割強であったが、今回は本人の収入を尋ねておらず、収入は世帯収入を尋ねた。そして、コロナ禍での「不安」「心配」の有無を尋ねた質問では、「あてはまる」「ややあてはまる」を足すと6割を超えた。その質問項目の自由記述には、在日コリアンだから受ける影響(78件)、あるいは女性だから受ける影響(70件)について言葉が寄せられていた。
最後の自由記述は196人の記述があった。内容を見ると、民族差別に関するコメントが122件、性差別に関するコメントが54件、その他のコメントが74件である(1人のコメントに内容が2つ以上の場合有)。
今後の課題として、(1)コロナ禍での調査の困難さ、(2)アンケートの調査票を広く届けることの困難さー本当に困っている在日コリアン女性に届けることができたのか、(3)アンケートの調査票の作成における複合差別の問題設定の難しさの3点を挙げておきたい。
そして、この調査プロジェクトを通じて、私たち自身が知り、当事者から学び、当事者にエンパワーされる経験をした。「拡がり、つながり、ともに立ち向かう」を合言葉に、すでに連携をしてきた他のマイノリティ女性グループとのネットワークを強めながら、活動を前へ進めていきたい。
永吉希久子さんのコメント
「貴重な調査であること共有し、よりよい調査への提言をする」
<在日コリアンへの量的調査の難しさ>
在日コリアンを対象にした量的調査がそもそも非常に難しい。一般的に社会調査は限られた対象を通じて、社会全体やある集団全体のことを知ろうとするもので、その結果を一般化するには代表性が高い人を選んで調査する必要がある。一般には、対象となる集団に属する人全体が載っている名簿などからランダムに抽出するなどして万遍なく選ぶ。しかし在日コリアン全員が載っている名簿はない。研究者であれば住民基本台帳から外国籍者を選んで調査票を送ることは(適切な手続きと条件の下では)可能であるが、日本国籍の在日コリアンは対象から外れてしまう。過去に実施した民族団体による量的調査はその団体等が保有する名簿がベースである。行政がエスニシティを把握していないことが調査を実施するうえでの問題となるが、行政がそれを把握することがプラスになるとは限らない。国家などがこうした名簿を人権侵害に利用した歴史を研究者は伝えている。行政がこうした調査するのであれば、その過程には当事者の関与が必要であるし、行政ではなく、研究者や当事者団体中心の調査のほうが望ましいかもしれない。
在日コリアンを対象とした調査の難しさには、回収率の低さも関わる。かつては直接対象者に対面で質問に答えてもらう訪問面接調査をしており、その時は回収率が高かった。今日ではプライバシーの問題もあり、訪問面接調査は難しくなりつつあり、郵送調査が実施されることが多い。一般に、郵送調査の回収率は訪問面接調査に比べ低いが、在日コリアンの回収率は特に低い傾向にある。たとえば大阪市の外国籍住民に対する調査(2019年)の回答者のうち、特別永住者の割合は28.1%、韓国・朝鮮籍者は37.4%だった。2019年に大阪市に居住している外国籍者のうち、特別永住者は34.0%、韓国・朝鮮籍者は44.8%だったのと比べると、ともに低い割合となっている。これは、特別永住者や韓国・朝鮮籍者の調査への回答率が低かったことを意味している。高い回収率が得られないため、在日コリアンの状況を知ることができるだけの十分な回答を得ることは難しくなっている。
このような難しさがあるため、公的統計を分析すればよいと考える人もいるかもしれない。たとえば国勢調査では韓国・朝鮮籍の人々の学歴や職業分布が日本国籍者に近いことはわかる。しかしこの調査の目的は差別状況の把握ではないので、差別の状況を知るための十分な情報は得られない。収入状況の公的調査として「賃金構造基本統計調査」があり、2019年より在留資格も調査項目に含まれたが、特別永住者は対象外で、日本国籍者と同じ扱いになっている。ニューカマーの外国人については公的調査によって生活や雇用の状況について把握できるようになってきているが、そこから特別永住者がこぼれ落ちている。
私自身が実施した社会調査では、例えば、韓国・朝鮮籍の人々のメンタルヘルスの状態の悪い人が日本人よりも多く、そこに被差別体験が影響していることが明らかになった。ただし私の調査は外国籍を対象とし、日本国籍のコリアンは対象外であるのに加え、個々の国籍の人の人数が少ないので、ジェンダーによる違いや内部での多様性は十分把握できていない。
<本調査の意義の大きさ>
こうした状況を考えると本調査の意義は大きい。まず在日コリアン女性だけで500人というのは規模の大きい調査なので、内部の多様性が明らかになっている。これは、李月順さんの今回の報告ではふれられなかったが、報告書を読むと、その結果として在日コリアン女性の経済状態が二極化していることがわかった。また、李月順さんの報告にあったように、子どものいる在日コリアン女性の60%以上が子どもが差別を受けるかもしれないと心配していることや、ニューカマーの韓国人で孤立している人の存在が明らかになったことも重要である。さらに、自由記述やインタビューの活用により、統計には現れない様々な思いや経験が描かれている。日常的なマイクロ・アグレッション、制度的差別や在日コリアン女性であるゆえの抑圧などが明らかにできたことも意義がある。
<「偏り」を考慮することの大事さ>
本調査は大きな意義があることを強調した上で、量的調査なので「偏り」の有無も把握しておきたい。実は在日コリアン全体の状況がわかる統計がないので、本調査のデータにどのような偏りがあるかは実際には把握できない。そこで暫定的に国勢調査での韓国・朝鮮籍女性のデータを用いて、年齢、居住地域、配偶者関係、学齢、雇用関係、職種などを本調査と比較した。「韓国・朝鮮籍の女性」全体と比べると、本調査は、「相対的に経済的に安定した、配偶者を持つ、大阪の居住者を中心としている」人たちがより代表されている可能性がある。このことを念頭において、結果を見る必要があるだろう。
<今後の調査への提案>
今後の調査をするうえでは、無作為抽出での調査を重視するかどうかをまず考える必要がある。そのうえで、重視する場合は、集住地域での住民基本台帳からの無作為抽出や、同じく集住地域での住宅地図などを使ってのエリア・サンプリングで住居を無作為抽出する方法がある。民族学校の保護者などの名簿が利用可能なら、それを用いてのサンプリングすることもありうる。いずれにしても量的な方法を取るのであれば、「在日コリアン女性であることによる困難」を浮かび上がらせるという目的のために、日本人女性や在日コリアン男性などとの比較の視点があったほうがいいと思う。
無作為抽出を重視しないという考えもあるだろう。今回の報告書を読んで、自由記述やインタビューから伝わるものが重要であると思った。全体の何%だから問題であると言うのではなく、実際にそう感じている人が少なくないことが重要ということだ。また、インタビューで語られた内容はだれかと比較する性格のものではない。ただし、聞いた人たちにどういう偏りがあるかは考慮するべきである。なぜなら、調査の協力者の声を拾いあげることは重要であるが、同時にこぼれ落ちたり、聞こえなかったりした声を考える必要があるからである
※『第3回在日コリアン女性実態調査』報告書(A4、144頁、800円)
申込・問合せは apeuro.inthefuture@gmail.com