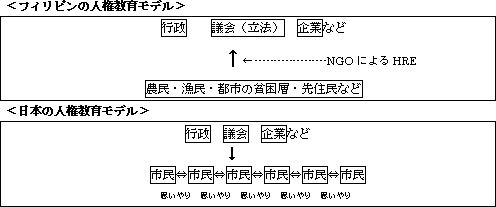ヒューライツ大阪は
国際人権情報の
交流ハブをめざします
- TOP
- 過去アーカイブ(これからの事業)
- フィリピンの人権教育についての雑感
フィリピンの人権教育についての雑感
阿久澤麻理子(姫路工業大学助教授)
1963年生まれの私は、「国際ばか」世代である。戦後教育改革の一環として始まった国際理解教育は、日本の高度経済成長と、企業の海外進出の増加を受けて、1974年の中教審答申以後は世界に「通用する」日本人の育成をめざして、英語教育や国際交流などを中心とする内容へと変化していった。ご多分にもれず、わたしもこうした「外向き」の、ほとんど外国理解と同義である国際理解教育を受けた世代である。だから最初の私のアジアとの出会いもこうした「外国に対する」好奇心、いわば外向きの関心からの出会いだった。
しかし、アジアの国々を知るにつけ、単なる異文化交流への関心ではすまないことを痛感した。第二次大戦中の歴史、そして当時増加しつつあった、アジア各国への進出企業の問題(1980年代から企業の進出先は欧米からアジアへとすでに移りつつあった)、そして日本のODAの問題などをくぐらなければ、本当の日本とアジアの関係はみえない。そうした思いから、ようやく大学生になったころ、草の根の開発援助団体などの活動に関わりながら、アジアを見るようになった。
しかし、こうした経験から、日本とアジア、日本とフィリピンの関係をとらえなおす視点を得た一方で、わたしの中に「アジア=援助対象国」というステレオタイプが形成されてしまったことも事実である。植民地支配と開発独裁によって、社会構造の問題を抱えるアジア、貧しいアジア、だから援助を必要とするアジア、という見方である。
こうした自分のステレオタイプを壊し始めるきかっけを与えてくれたのが、アジアの人権教育との出会いである。フィリピンの人権教育との出会いからは、とりわけ大きな影響を受けた。フィリピンをはじめ、アジアの多くの国々は、数百年に渡る植民地支配を受け、また独立の後も開発独裁を経験した。そして今日では、グローバリゼーションの中で受ける人権侵害も深刻化している。こうした気の遠くなるほどの年月におよぶ経験の中で、アジアの人々の人権に対する感覚と思想が共有され、とぎすまされてきたように思う。そして現在、各地で進む民主化運動が契機となって、こうした蓄積が、人権の擁護と伸長のための法・システムの整備、人権教育への取り組みなどとして、急速に具体的な形をとりつつあることに気づかされたのである。
「フィリピンのような貧しい国で人権教育が進んでいると聞いてもピンとこない」という言葉は、わたしがフィリピンの人権教育のことを伝える機会をもつごとに、必ず誰かから返されてくる声の一つである。たしかに、新聞などで見聞きするフィリピンは、圧倒的な貧困、官僚の汚職などの問題多き国かもしれない。だが、人権を実現しようとする人びとの熱意と行動力からは、むしろ私たちが学ぶべきことが多い。
フィリピンでは、マルコスによる独裁が民衆による革命によって打破された後、詳細な人権規定をもつ新憲法が制定され、その中に「人権教育は国家の義務である」ことが位置付けられた。これを受けてあらゆる教育機関が人権教育を既存の教育・研修プログラムの中に組み込もうとして努力している。もちろん、制度ができても、それがどの程度順調に執行されているかの問題は残るが、現在のフィリピンの動きは、人びとの長年の人権に対する想いと蓄積とが、機会をとらえて、いっきに花開きつつあるかの感がある。人権はそれを希求する人びとによって、もっともよく実現されるのだ、と実感させられる。
また、私がもう一つ学ぶところとなったのは、NGOの働きである。フィリピンではマルコス時代の膨大な人権侵害に対して声をあげ、民衆の権利擁護のために活動してきたNGOが数多くある。民衆に人権とは何か、人間はどのような権利を持つのか、それはどのようにして実現すべきなのか、ということを伝えてきたのはNGOである。そして近年は民主化の動きが進展する中で、今まで政治的な場への参加を阻害されていた農民、漁民、都市の貧困層などが、自らの権利を守るために発言し、政治的プロセスに対して効果的に影響を与えられるよう、NGOが人権教育を実施している。
政府機関や行政が人権教育に取り組むことは、環境の醸成や、あるいは公権力を行使する立場にある「特定職業従事者」の人権意識を高めるなど、多くのメリットもある。しかし、草の根の民衆が権利意識に目覚め、その実現を求めて政府や行政に対して声を上げることを可能にするような人権教育をどこまでおカミが徹底できるか、といえばムリである。民衆が、自らの問題を「意識化」し、その問題解決を社会に訴えていく力をつけさせるという点において、フィリピンの人権教育モデルは図のようになっている。
一方、日本は問題を社会に持ちこむというよりは、私人間の配慮や「おもいやり」で問題を解決しようとする志向性が最近より強まっているように思う。しかし、フィリピンのモデルに比べてみれば、これは、日本の人権教育が、主に地方自治体や教育委員会などの組織によって実施されるがゆえの限界でもある。人びとが自分の権利を学び、権利を実現するための方法やプロセスについて知るような、エンパワメントのための人権教育を実施するには、市民社会、NGOが力をつける必要がある、と実感する次第である。